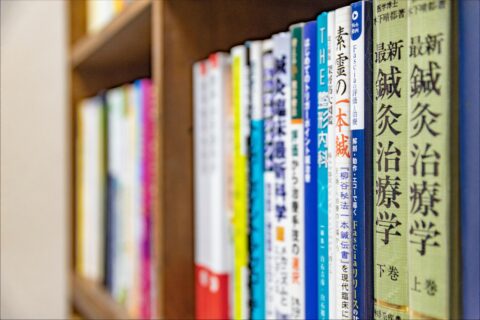概説
鍼の効く疾患は、血液循環障害による疾患です。
これは、どういうものかというと、血液の循環が障害されて起きた疾患です。
血液循環障害による疾患とは、例えばガチガチの凝り固まった不調とか神経痛の痛みです。神経は筋肉と筋肉の間や、筋肉の中を通るので、筋肉の硬さが神経に悪影響を与えやすいのです。
例えば坐骨神経痛、腰痛、また急性の寝違いやギックリ腰などは鍼で治ります。来たときは杖をついてきていても、また頸を回すことが出来なくても、鍼を抜いた途端に自由に動けるようになり、頸を回すことが出来るようになるのです。もっとも、こうした急性症状に対する一発効果があるので、鍼灸を希望する人は後を絶たないのです。
鍼で治る痛みは、血液循環障害による痛みです。つまり筋肉の痛み。
鍼で治らない痛みは、骨の変形や椎間板突出による痛みです。このような場合は病院で検査を勧めます。
筋肉の痛みかどうか知るためには、自覚症状に頼らなければなりません。
原則として、血流が悪くなると痛みが増すのです。
具体例
① お風呂に入ると、痛みが和らぐ。
温めると、その部分の筋肉が柔らかくなるので、血液循環が良くなります。だから温めて痛みが和らげば、まず血液循環障害なので、鍼治療の対象です。中国医学では「温まれば血流が良くなり、冷えれば血も凝固する」といって、曇りや雨など、寒い日に鍼治療してはならないと書かれています。このため、鍼施術をする時は室温が25~28℃になるよう調整しているのです。
② 酒を飲んだ翌日に、痛みが悪化する。
酒を飲むと血液循環が良くなるから、痛みが悪化するはずがないと思いたい人が多いようです。
確かに酒を飲むと、一時的に毛細血管が広がって赤くなり、体温も上がります。しかし、そのあとで寒気を感じます。 これはアルコールが発熱し、熱を逃がすために体表の血管が広がって赤くなり、体温が上がりすぎないように一定に保とうとするからです。しかし脳は酔っぱらっています。つまり麻酔が効いているわけですね。そこで調子に乗って体温を放出していると、予定の体温より下がってしまう。「これ以上に体温が下がったら、死んでしまう」と、脳としては体温放出を止め、慌てて血管を縮めにかかるのです。そのときに鍼で広げた血管まで閉められてしまうのです。それで鍼の治療効果はストップ。
③ 寝ていると、夜中や明け方に痛みが出る。
寝ていれば、使っているわけでなく、むしろ休めているのに痛みが出る。これは非常に不思議です。
実は、人間は夜行動物ではなかったのです。だから日中にエサを探すなど動き回り、夜はおとなしく眠っていたのです。動き回るとなれば、心臓は馬車馬のように動いて、手足に血液を送り込み、十分な酸素を供給しなければなりません。しかし心臓も休息しなければ疲れてしまいます。そこで手足を動かす必要のない夜間には、心臓の鼓動が穏やかになり、血圧も低くなります。すると収縮した筋肉には、筋肉に血管が押さえつけられているので十分な血液が供給されず、酸素不足となって筋肉が硬直し、神経を締め付けて痛み始めるのです。これも血圧が低くなると血流が悪くなるから起きる現象です。
④ 運動したあとは痛みが悪化する。
これは筋肉が収縮していると、その筋肉内の血管が圧迫されて血流量が少なくなり、その少ない血液から運動に必要な酸素を取り込むので、結果として運動すればするほど血液や酸素不足となり、筋肉収縮が強くなって神経を圧迫するため、痛みが悪化するのです。だから縮んでしまった筋肉は、それに見あう血液量の運動しかできないのです。これも圧迫された血管の血流量が少ないから起きる現象です。
こうした症状に心当たりがあれば、それは鍼を縮こまった筋肉へ入れて緩めることにより、圧迫された神経と血管を開放し、痛みから解放です。